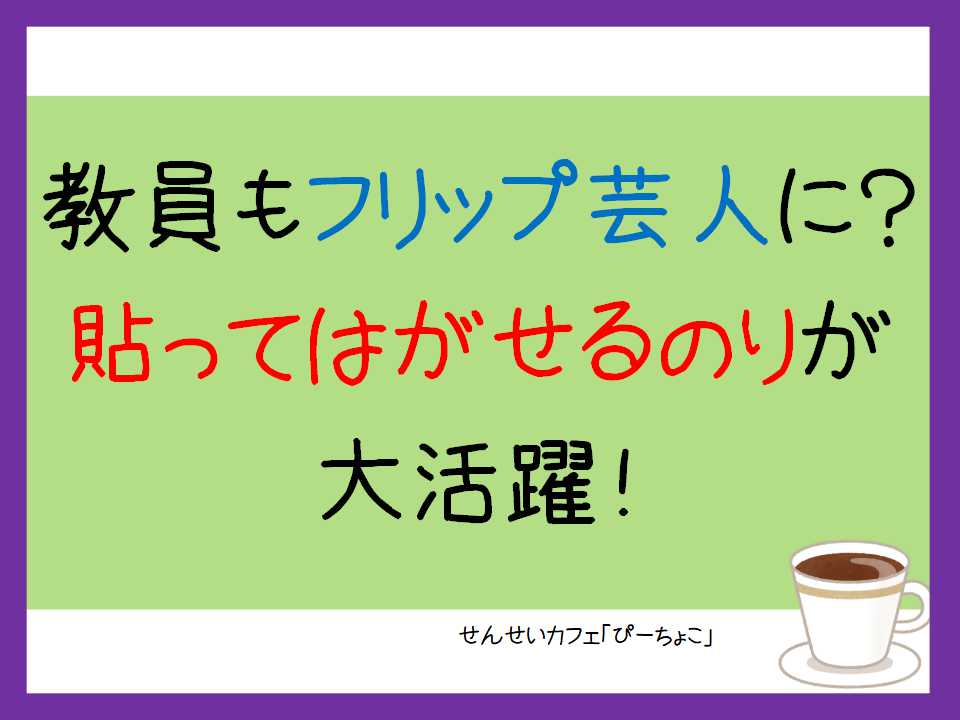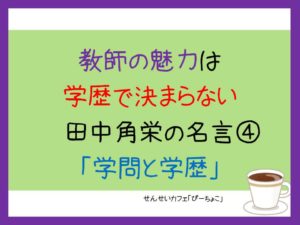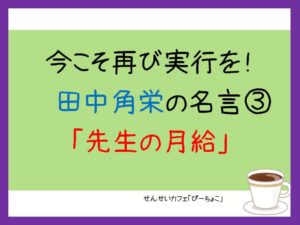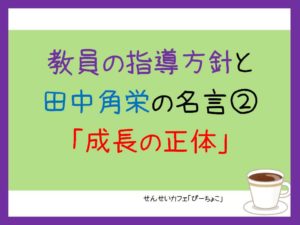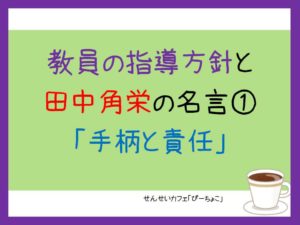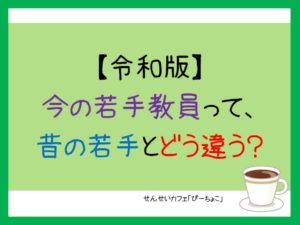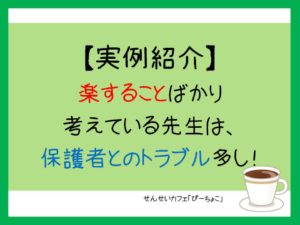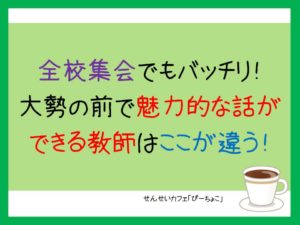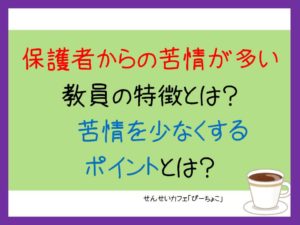今回は、授業のちょっとしたアイデアです。短い記事ですので、3分程度でさらっと読めます。
早速ですが、フリップ芸人のおもしろさってどこにあるでしょう?
それは、視覚にうったえるところにあるからだと思います。次は何が出てくるのかな?とワクワクしますよね。
あわせて、フリップをめくることによるテンポの良さも、興味を引き付けます。
フリップと言えば、ニュースでも大活躍しています。その際、フリップには隠されている部分があって、それをはがしながら説明しますよね。
実はこのアイデアは、授業でもおおいに役立ちます。
毎回準備するのは大変ですが、時間があるときに準備をしておきたいですね。子どもの食いつき方が違います。
フリップの隠された部分には何があるかというと、教師が重要だと思うこと、教えたいことだと思うかもしれません。
もちろんそれも大切ですが、時にはボケてやるのも一つのアイデアです。
例えば、社会科の授業でフリップを使うとします。まじめに教えたいところでは、
聖徳太子は、冠の色で位を分ける「*****」を制定した。
 ぴーちょこ
ぴーちょこ当然、ここに入るのは「冠位十二階」です。
しかし、最初は食いついていた子どもたちも、まじめなフリップが続くとしだいに飽きてきます。そうなったら、途中でボケを入れてやると笑いがとれて気分がリセットされます。
東大寺の建立の功労者といえば、「*****」と言っても過言ではない。



歴史が得意な子なら、「行基だ!」と答えるところですが、ここにボケた答えを入れてあげましょう。よくあるのは「大工さん」ですね。
ただ、この「*****」の部分をどうやって作るとよいでしょうか?
それには、「貼ってはがせるのり」が便利です。はがしやすいですし、何回も貼ったりはずしたりできます。
そして、フリップには何を使ったらよいのか。私の場合は、スケッチブックです。



さすがに芸人のように、投げ捨てるわけにはいかないですよね。
スケッチブックを使えば、散らかることはないですし、保管もしやすいです。
一度作ったものは、とっておけば何年も繰り返し使えるので、表紙がしっかりしたスケッチブックを使用するのが便利です。
子どもたちに見せることを考えると、サイズは大きい方が良いです。A3サイズがおススメです。
授業をおもしろくするアイデアとして、フリップを使ってみてはいかがですか?