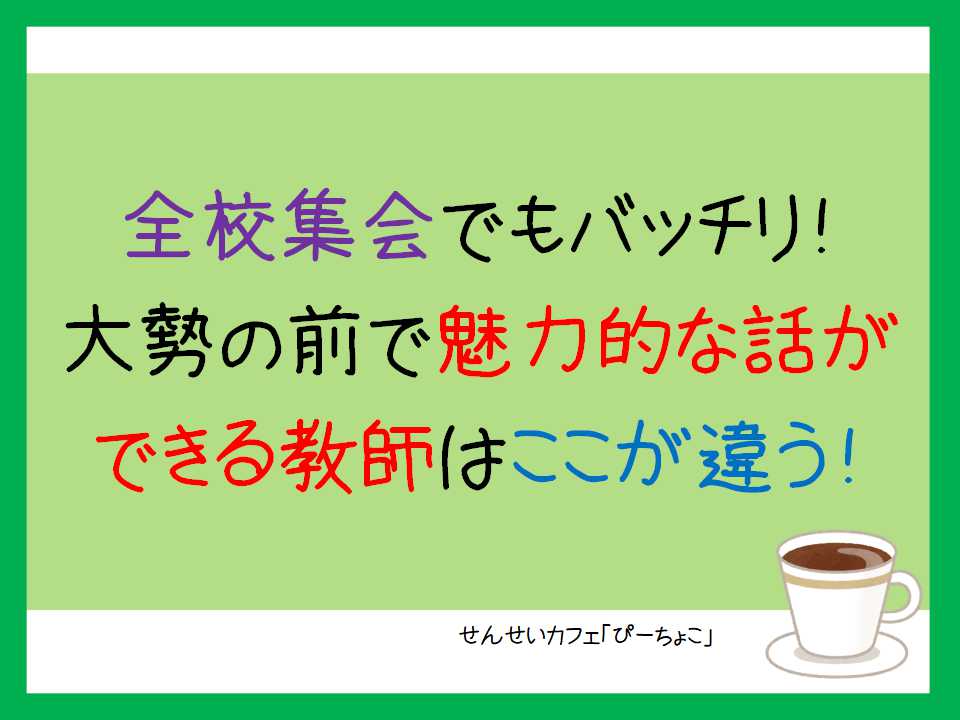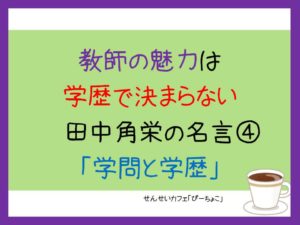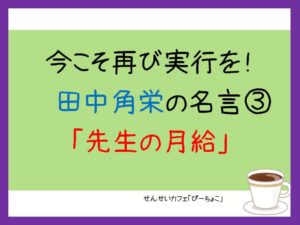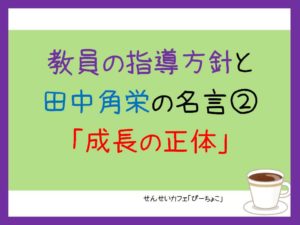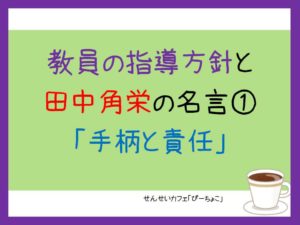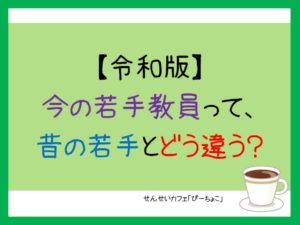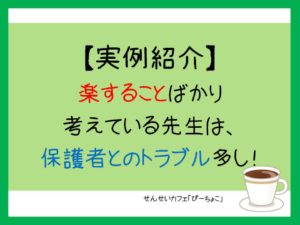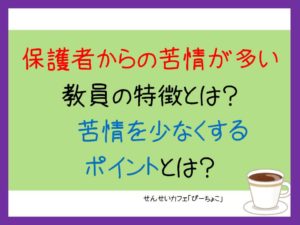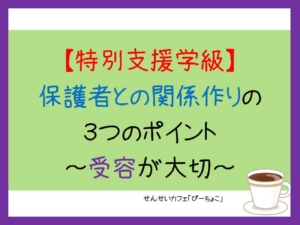教師の仕事において、人前で話をすることは避けて通れません。上手に話ができる教師に誰もがなりたいと願いますよね。
しかし、中にはこんな先生が周りにいませんか?
「私、人前で話すのが苦手なんだよね…。」

教師をやっている以上、そんなことを言う人はほとんどいないかもしれません。でも、口に出さないだけで、人前で話すことが苦手だと感じている先生はいると思います。
でも、大丈夫です。ポイントを押さえれば、誰でも魅力的な話ができるようになります!
今回は、全校集会で話をすることを想定し、そこで魅力的な話をするためのポイントについてご紹介していきます。
私は元教員ですので、教員の視点から教員にとって参考になるポイントが紹介できたらと思っています。
魅力的な話し方ってどんな話し方?
YouTubeを探せば、スピーチが上手な人の動画をいくらでも見つけることができます。
参考として、オリラジの中田さんの近畿大学でのスピーチを紹介します。この動画を見るだけでも、たくさんのヒントが得られると思います。
魅力的な話し方とはどんな話し方かを考える前に、逆の考え方で、聞いていておもしろくない、つまらない話をイメージした方が早いかもしれません。頭に思い浮かべるだけでも、いろいろと出てきませんか?
- 話の内容がおもしろくない
- 内容がわかりにくい
- 声が聞き取りづらい
- 話し方が単調で眠くなる など
人の話を聞いて、「これはよくない」と感じる部分が自分にできているか、そこを振り返るだけでも、何をしたらよいか見えてくると思います。
 ぴーちょこ
ぴーちょこダメな話し方をイメージした上で、もう一度中田さんのスピーチを見ると、「ああ、なるほど」と気付くことがたくさんあると思いますよ。
魅力的な話し方にするための基本的な考え方
緊張してもいい!


よく、「人前で話をするのに、緊張しない方法はありますか?」と若手の先生に聞かれたことがあります。
私はこう答えます。
「緊張してもいいじゃん。緊張するのはうまく話したいからでしょ。私(ぴーちょこ)だって緊張するよ。」
緊張の程度は人によって違うかもしれませんが、緊張するのは当たり前だと思います。私は緊張することが悪いことだとは感じていません。むしろ、適度な緊張感は必要だと思っています。
でも、手足が震える、のどがカラカラになるといった極度の緊張状態になって、話をするどころじゃなくなるんです!という先生がいらっしゃるかもしれません。
でも大丈夫です。私も教師になりたてのころはそうでした。でも、きちんと準備をしておくこと、場数を踏むことで、極度に緊張することはなくなっていきました。
笑いをとれる教師でなくてもいい


私、人を笑わせることが苦手…
人を笑わせるのが苦手だから、魅力的な話ができないと考えている先生がいるようです。でも、教師にとって「魅力的な話=おもしろい話」ではありません。
子どもたちにとって魅力的な話になればよいのですから、笑いをとることが必ずしも必要とは限りません。
逆に、おもしろいことばかり言う、悪く言うとただ笑いをとるだけでよいというものではありません。
教師として全校の子どもたちに話すのですから、大切なのは子どもたちにとって役に立つ話をすることです。子どもたちにとって役に立つ話をしても、聞いてもらえなければなりません。
その一つの方法として笑いをとって気を引くというのは、確かに方法の一つです。しかし、笑いをとるのが苦手という人が、無理してまで笑いに走る必要はないと思います。



もちろん、ちょっと冗談を言うことができる教師であってほしいですけどね。
回りくどくなってしまいましたが、何が言いたいかというと、
それぞれの先生の個性を生かせばいい
ということです。笑いを取るのが苦手であれば、それに代わる方法をとればいいのです。
魅力的な話にするための具体的なポイント


話の構想を練っておく
当たり前のことです。ノープランで全校児童生徒の前に立って話をしたら、きっとあなたにとってツラい時間となります。きちんと話の構想を練っておきましょう。
起承転結を作る
話が単調だと眠くなりませんか?例えば、夏休みの過ごし方について話をするときに、
今から夏休みの過ごし方について話をします。夏休みの過ごし方で気を付けることは3つです。一つ目は・・・・・・・・・・(中略)・・・・・以上、3つのことを守って、楽しい夏休みにしてください。これでお話を終わります。
という感じで話をしたら、子どもたちはどんな反応をすると思いますか?こんな程度の話をするのでしたら、「プリントを配りました。読んでおきましょう。」と言ってもいいくらいです。
話には起承転結を作りましょう。
授業と同じですが、話の導入つまり「起」の部分が大切だと思います。ここで子どもの心をぐっとつかむことが大切です。
「夏休みの過ごし方で気を付けることは3つです」と言うよりも、「実は、先生は夏休みに海へ行って大物を釣り上げるという目標があります。」と言った方が子どもの気を引きますよね。「ん?なんの話をするんだ?」という感じに。
そこから、水の事故に注意する話へもっていったほうが、ただ「水の事故に気を付けてください」と言うよりも効果的です。
まずは子どもの心をつかむことから。起承転結の「起」を特に意識して、話の構想を練ってみてください。
話が長くならないように
話し上手の人なら、聞く人を飽きさせないテクニックで長々と話ができます。
しかし、この記事をご覧の方は、きっと人前での話し方に苦手意識がある人、またはそこまで苦手意識はなくても、さらに上手に話ができるようになりたい人だと思います。
魅力的な話ができるぜ!と自信がある人でなければ、話の時間は極力短くするのがベターです。
先ほどの続きになりますが、「起」の部分がうまくいって子どもたちが関心をもってくれたとしても、話が長いとだんだんダレてきます。
ですから、時間が決められていないのなら、話は短くするべきです。
ただし、話すべき内容はしっかり盛り込んで、余分なことはそぎ落としていきましょう。先ほど例に挙げた夏休みの過ごし方について話をするならば、3分、長くても5分くらいで十分だと思います。
子どもたちにとって、「え?もう終わり?」くらいに思わせておいた方がいいですよ。次を楽しみにしてくれる子も出てきますから。
話し方に気を付ける
よく聞こえる声の大きさで、はっきりと
どんなにすばらしい話をしても、声が聞こえなければ意味がありません。また、声の大きさがよくても、ボソボソと不明瞭な話し方では、聞く人に伝わりません。
マイクを使わないなら、しっかりと声をだすこと、マイクを使うなら、ゆっくりハキハキと話すことを意識しましょう。
実は自分がどんな声の大きさで、聞く人にどのように聞こえているのか、自分ではわかりにくいものです。一度、録音または録画して確認するとよいです。
私も自分の話し方を録音して聞いたことがあります。あまりのひどさにビックリしましたが、自分の話し方で直すべきところがよくわかりました。
話し方に抑揚をつける
職場に話し方の上手な先生がいますよね。話の上手な先生は、話し方に抑揚がついているはずです。具体的には、
- 話の大切なポイントになると、話し方がゆっくりになる。
- 声のトーンの高い、低いを使い分けている。
- 急に話を止めるなど、話の間をとっている。
「話す」のですから、「読む」わけではありません。話の構想を練っておいても、それを読んで聞かせるのではなく、抑揚をつけた「話す」へ上手に変換していきましょう。
目線と表情に注意を
目線は授業と同じです。聞く人の目を見ながら話しましょう。
表情も大切です。緊張した表情では、聞く方も何となく緊張していしまいます。基本は笑顔でいると、聞く方も緊張がほぐれます。
新型コロナの感染対策のため、マスクを着用して話すことが基本となっています。しかし、笑顔でいるのは目元を見てもわかります。マスクをつけていても表情を意識しましょう。
「えー、」とか「あー」とか言わない
話の上手な人、話すことの頭に、「えー」とか「あー」とかほとんど言いません。
かつて、義家弘介さんの講演会に参加したことがあります。お話のなかで、「人前で話すためにいろいろと努力した」ことを言っていました。「えー」とか「あー」を言わないようになんてことは一言も言っていませんが、義家さんはほとんど言っていませんでした。
YouTubeでいろいろな人の話し方を聞いてみてください。「えー」とか「あー」に注目すると、本当にヒドイ人がいることに気付きます。



それ、うちの校長です!という先生、いますよね?
気になりだしたら止まらなくなると思います。
もし、自分がすぐに「えー」とか「あー」と言う自覚があるならば、普段の授業で強制していきましょう。
「えー」とか言ってしまうのは、それを言っている間に次の言うことを考えているからです。早口の人に多い気がするので、少し話し方をゆっくりにするだけでも改善されていくと思います。
適度に笑いをとる
記事の前半部分で、「子どもたちにとって魅力的な話になればよいのですから、笑いをとることが必ずしも必要とは限りません。」と書きました。
もちろんその通りなのですが、適度に笑いが起こる方が緊張がほぐれてよいと思います。
ただし、小学校と中学校では笑いのツボが違いますし、どんなことで笑いをとってよいのかわからないという人もいるでしょう。
そういう人は、自虐ネタが一番簡単です。間違っても、誰かをネタに笑いをとってはいけませんよ。先生がいじめを助長する発言をしたと揚げ足をとられても困るので…。
別にお笑い芸人ではないので、爆笑が起きなくても大丈夫です。苦笑いでも構いません。ただ、何となく空気が和めばよいのです。
視覚に訴える
言葉だけでは魅力な話をするのに自信がないという先生。
効果的なのは、視覚に訴えることです。大人だって話を聞くより、何かを見せてもらいながら聞いた方がわかりやすいです。
視覚に訴えるよさは、話の内容をわかりやすくするということだけでなく、子どもの視点を話し手に向けさせることができることです。
例えがあまりよくありませんが、校長先生が何も見せずにおもしろくもない話を長々としていたら、子どもたちはどこを見ていますか。横を向いたり下を向いたりしますよね。
全校の子どもたちの前で話をする機会がそれほどない場合は、準備にかける時間もとれると思います。
ぜひ、視覚に訴える資料を作って話をしてみてください。視覚に訴える資料は本当に効果的で、話し方に自信がないという先生でも、資料次第で子どもたちが最後まで集中して話を聞くことができます。
それでは、視覚に訴える資料にはどんなものがあるでしょうか。メリットとデメリットを交えていくつか紹介します。
フリップ
プレゼンソフト(パワーポイントなど)
実物
話の内容に関わる実物を見せます。例えば、交通安全の話であればヘルメット、水難事故防止の話ならライフジャケットを見せるといった感じです。
最後に


ここまでお読みいただき、ありがとうございます。参考にしていただけることがあれば幸いです。
人前で話すことは、場数を踏むことでかなり慣れてきます。しかし、慣れればよいものでもなく、魅力的な話になるよう努力をしながら慣れていくことが理想です。
そうでないと、魅力的な話ができないまま、教師経験だけが長くなっていきます。やがては、話のおもしろくない先生として周りから思われると同時に、自分自身も向上心をなくしてしまいます。
今回は、全校の子どもたちの前で話すという場面を想定して、そこでの魅力的な話し方についてまとめてきました。
教師は毎日の授業の中で、子どもたちの前で話すことができます。毎日が実践の場となりますので、できることは意識して毎日続けてみてください。半年でも驚くほど変わります。
特に、「えー」とか「あー」を言ってしまう先生は、言わないように意識することを毎日続ければ、劇的に変わっていきます。
「○○先生は、話が上手ですね」と周りから言われる先生になりたいですね。