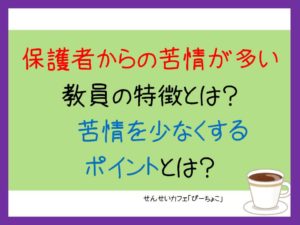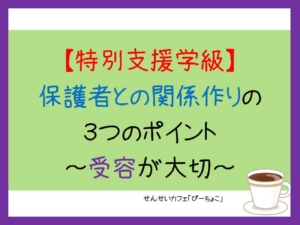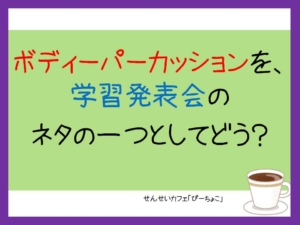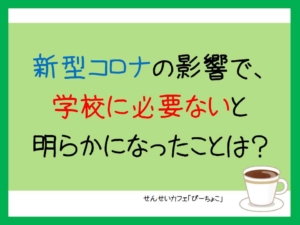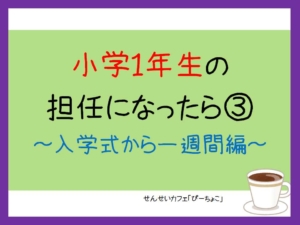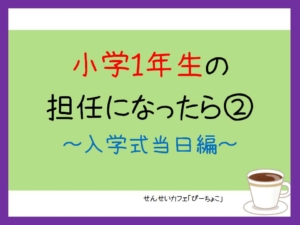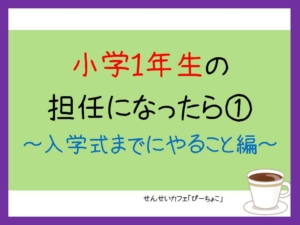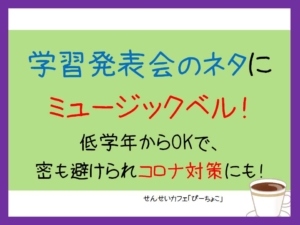どうも。元公立学校教員のぴーちょこです。
今回は保護者との懇談会について、準備から当日までのポイントについて、教員歴20年のぴーちょこが偉そうにご紹介します。小学校での教師と保護者の二者懇談を対象としていますが、中学校での三者懇談にも参考になるところはあると思います。

どの小学校でも、保護者との懇談が年に何回か実施されていると思います。中には懇談が得意な先生もいるでしょう。
しかし、若手の先生、とりわけ初任者の先生にとっては、「心臓バクバクどうしよう!」という状況なのではないでしょうか。私もそうでした。そのため、今回の記事は、ぴーちょこが失敗したからこそ学んだことも紹介します。
懇談を有意義な時間にするためには、やはり準備が必要です。
ベテランの先生は余裕に見えますが、うまく懇談ができる先生だって必ず準備はしています。それが紙に書いたことか、頭の中で整理したことかはわかりませんが、必ず話す前に何かしらの準備はしているはずです。あとは、長年の経験による「話術」というスキルを武器にしています。
保護者と話すことが苦手という先生もいるでしょう。
でも、話すことが苦手な先生でも、しっかりと準備をしてきちんと保護者に伝えることができれば、保護者に理解してもらえます。
逆に、話すことが得意でも、薄っぺらい内容しか話せなければ、保護者は「うちの子をきちんと見てくれているのかな?」と心配になるかもしれません。
個人懇談は、子どもの成長のための情報交換という場ですが、同時に保護者との信頼関係を築く絶好のチャンスでもあります。ぜひ計画的に準備をして、当日に臨んでください。
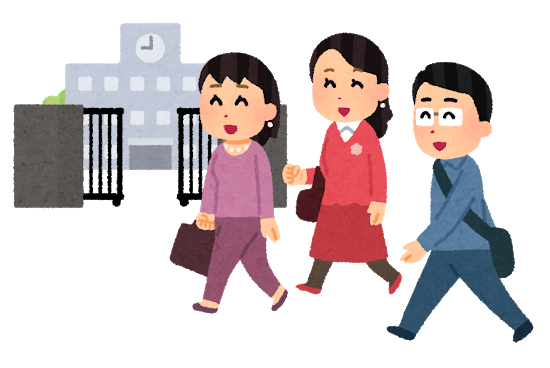
個人懇談までの準備
懇談の日程を調整する
懇談希望を聞いて、日時を調整します。まあ、これについては、全校一斉に取り組むので、わからないところは周りの先生に聞きましょう。
兄弟関係があるところは、同じ日で時間が近くなるようにします。
父子家庭や母子家庭など、仕事の都合がつけにくい家庭から組み、日時を問わない家庭を後から組んでいきましょう。また、時間が押して懇談予定がどんどんずれていかないよう、3~4家庭続くようなら、少し空きの部分を作っておきましょう。時間調整のためです。
懇談の日程を組んだら、保護者から聞き取った予定表と照らし合わせて、保護者の都合が悪いところに予定を入れていないか、必ず確認してください。ここを間違えると、懇談の前に不信感をもたれてしまいますよ(涙)。
最終確認として、懇談の日程の中で、自分の出張がないか必ず確認してください。
私は採用されて一年目の年、4日間行われる個人懇談の内、1日が初任者研修に該当していることをすっかり忘れていました。
気付いたのが、懇談の決定通知を出した後だったため、7~8家庭に謝罪して、予定を変更させてもらったことがあります。決定通知を出したすぐ後に気付いたのでよかったのですが、もし当日に気が付いたとしたら…ゾッとします。
 ぴーちょこ
ぴーちょこ実は自分で気が付いたわけではなく、学年主任の先生に指摘されたんですけどね…。みなさんも気を付けて!
保護者情報を調べておく


懇談の前に、どんな保護者か情報を得ておくと、気持ちの上で少しは安心できます。また、必要な対策も事前にできます。具体的には、以下のような情報を得ておくとよいでしょう。前担任や兄弟関係を受け持っている担任などに話を聞いてみましょう。
- クレーマー系の保護者かどうか(重要!)
- 父子、母子家庭の場合、近くに助けてくれる親類などがいるか
- 保護者が同業者(教員)であるか
- 話しやすい保護者であるか
クレーマー系の保護者であれば、聞くまでもなく学級を受け持つときには知っていることでしょう。嫌だなあと思いますが、きちんと対策を練っておき、丁寧に対応すればきちんと信頼を得ることができるはずです。もし、これまでの担任がその保護者の扱いの上手な先生だった場合、対応のコツをしっかり聞いておきましょう。
クレーマー系と言っても、前担任と合わなかっただけという場合もあります。
私も、前担任からクレーマーだから注意と聞いていましたが、実際には前担任の方に問題があったそうで、むしろすごく好意的に接してもらえたことがあります。校内の誰もが知っているようなクレーマーでない限り、担任の接し方次第で、きちんと味方になってくれるはずです。



ただし、中には誰が担任になろうと、学校への不満をタラタラ言う保護者もいます。言い返したいところですが、基本的に聞き役に徹しましょう。
また、家庭環境によっては、大変な思いをして子育てをしている場合があります。(母子家庭で頼る人がいない、父親が単身赴任で普段は家にいないなど)。
そうした環境を知っておくと、宿題を忘れがちなことを話す場合でも、「お仕事が忙しくて、なかなか宿題を確認するのは大変ですよね」と、保護者の気持ちを理解しながらの言葉がけができます。家庭環境を知っておけば、頭ごなしに「宿題をよく忘れるので確認してください」とは言わないですよね。



ただし、若手の先生は、複雑な家庭環境だと知っていても、あまり突っ込んだことは聞かない方が無難です。「若造に何がわかる!」と思う人もいるので。
保護者が同業者、つまり教員である場合、話す内容をしっかり準備していないと、「あまりうちの子のことを見ていないな」と簡単に見透かされてしまいます。まあ、同業者なのでお互い気を遣い合ってしまう場合が多いですが(笑)。
最後に、話しやすい保護者かどうかです。大人同士なので、ほとんどの保護者が普通に会話ができると思います。しかし、中には目を合わせられない、会話がほとんど続かないという保護者もいます。
こうした保護者の場合も、情報を得た時に、これまでの担任の先生にどうしたらよいか相談するとよいでしょう。


子どもの事実をまとめておく ~懇談メモの作成~
保護者が知りたいことは、以下の2点に集約されます。この2点について、きちんと答えられるように、懇談メモを作成しておくことが大切です。
① 学習についていけるか
② 友達と仲良く過ごせているか
この2点を正確に伝えるために、必ず一人一人の資料を用意しておきましょう。


学習について
得意な教科と不得意な教科を答えられるようにしておくのは当たり前です。具体的にどの単元が得意で苦手なのか、具体的に答えられるようにしましょう。テストの点をチェックすれば、すぐにわかります。
苦手としている学習については、学校ではどんな指導をしているかを伝えましょう。これを伝えないと、「先生は、うちの子が授業で困っていても何もしてくれない」と思われてしまいます。
学校での対応をきちんと伝えた上で、家庭ではどのような協力をしてほしいのか説明しましょう。なお、本人のがんばりもさりげなく褒めておくことがポイントです。



苦手な学習があることをはっきり伝える必要がありますが、断定的な言い方は保護者に威圧感を与えてしまいます。柔らかい表現で、本人のがんばりを褒めながら、家庭の協力も必要であることを伝えましょう。
もちろん、よくできている学習内容は、しっかりと保護者に伝えましょう。同じく具体的に何ができているのか伝えることが大切です。具体的なエピソードを交えながら話せるとよいでしょう。
懇談は学期末に行うことが多いですが、もし成績(評定)が出ているなら、懇談の資料として必ず用意しておきましょう。
保護者に「算数が得意でがんばっていますよ」と伝えたのに、実際は成績が下がっていたら保護者はどう思うでしょう。いい加減なことを言う先生だと思われてしまいますよね。
教師の思い込みは意外とあるものです。算数がよくできると思っていたのに、テストの出来はイマイチで、成績を出したら思ったよりよくなかったということは、私も経験があります。正しいことを伝えられるようにしておくことが大切です。
生活について


まずは友達関係についてです。学級では誰と仲が良いのか、休み時間に一人ぼっちになっていないか、保護者はとても気にします。
家で学校での出来事をよく話す子はよいのですが、思春期で自分のことを話さないという子もいます。具体的に誰と仲が良いのか答えられるようにしておきましょう。
また、係活動や掃除、給食当番などの取り組みについても、保護者は知りたいものです。家ではダラダラしていても、学校ではきちんと役割を果たせていれば、保護者は安心します。
伝えるときは、必ず具体的なエピソードを交えながら話しましょう。そのためには、普段からメモをとることをおススメします。これはいいなと思う行動をしていたら、ササっとメモしておきましょう。
子ども自身の振り返りについて
事前に子どもたちに学校生活を振り返らせるアンケートを実施すると、懇談のネタが手に入ります。私は、以下のような項目を聞いていました。参考にしてください。
- 好きな教科と嫌いな教科
- よく遊ぶ友達と何をして過ごすか
- 係や当番活動でがんばったこと
- クラスの中で、すごいと思う友達
- 習い事
- 今、悩んでいること
- これからがんばりたいこと
- 家の人に言いたいこと
懇談当日に気を付けること
次は、懇談当日に気を付けることです。前日までしっかり準備していても、大切なのは当日です。そこで、当日に気を付けるポイントをまとめました。


懇談時に必要なものを確認する
個人懇談の開催場所は、大体教室だと思います。教室に必要なものをきちんとそろえておきましょう。せっかく準備したのに、職員室に忘れてきたということがないようにしましょう。
懇談メモ
上記に紹介した、個人懇談で話すためのメモです。パッと見ても中身がわからないように、ファイルにきちんと綴じておきましょう。間違っても、プリントアウトしたメモをバインダーに挟むだけということはやめてください。のぞかれたら大変です!
懇談のメモと同時に、成績が出ているならそれも一緒に用意しておきましょう。
話題に必要なもの
算数で粘り強くがんばっているなら、取り組んだプリントを見せてあげましょう。とてもよい作文が書けたなら、それを見せてあげましょう。図工が得意なら、描いた絵や作った工作を見てよいところを伝えましょう。話すよりも実物を見せてあげた方がよく伝わります。
また、教科書やドリル類も近くに準備しておけば、家庭でどうやって教えてよいかわからないと相談を受けた時も、教科書やドリルを見せながら説明することができます。
笑顔で保護者を迎える ~メラビアンの法則~
メラビアンの法則と言って、話し手が聞き手に与える影響を数値化した実験結果があります。これによると、人の印象は視覚からが55%、聴覚からが38%と言われています。(こちらのサイトを参考にしました。)
保護者によい印象を与えるために、笑顔で迎えましょう。そして、気持ちのよいあいさつをしましょう。緊張して懇談に来る保護者もいますので、笑顔を見せて安心させてあげたいですね。



買い物に行ったとき、笑顔で気持ちよくあいさつしてくれる店員さんだといい気分になりますよね。第一印象って大事です。
褒めること9割を意識して伝える


「褒めること9割」を意識することが、懇談で最も大切なことだと思います。
懇談に来て、終始子どもの悪いところを聞かされたら、親はどんな気持ちになるでしょうか。通常の親であれば、学校の先生に言われるまでもなく、直さなければいけないことは知っています。極端な保護者だと、子どもが否定されるのは自分が否定されるのと同じだと感じます。
教師と保護者と多少の考え方の違いはあっても、子どもをよくしていきたいという目標は共通しています。その共通した目標を達成するには、保護者の協力を得ることが大切です。
できなくても子どもががんばっている姿を褒め、小さな行動でも見逃さずに褒めることが保護者の協力を得ることにつながります。
ただし、嘘を言っていいわけではありません。嘘は保護者にバレます。以下の点を参考に、保護者に話をしてください。
見方を変えれば、短所は長所になる
褒めるところがなかなか見つからない!と思う子がいると思います。しかし、それは教師が見つけていないだけです。
実際にたくさんの子どもたちを相手にしていると、よいところを見逃してしまいがちな子はいます。そういった子は、目立たない子です。
「目立たない子」という言葉だと、何となくマイナスのイメージを感じさせます。でも「目立たない子」という見方を変えれば、「手がかからず自立している」ということでもあります。
つまり、見方を変えれば、短所と感じられることでも長所になるということです。
- 挙手して意見を言えない → 意見を発表できないが、じっくり考えている
- 飽きっぽい → いろいろなことに興味がもてる
- おとなしい → 落ち着いている
もちろん、長所に変えられないようなこともありますが、見方によって変えられることもあるということを知っておいてください。
保護者から、「うちの子はおとなしいので心配です」と相談されても、「おとなしいのではなく、落ち着いているのですよ。よく周りを見て、冷静に行動できています。」と言われれば、保護者は安心すると思います。



ウソはいけませんが、子どもの個性を認めてあげることで、保護者は安心しますよ。
「こうするともっと良い」点を一つ伝える
「褒めること9割」ですが、「こうするともっと良い」という点を最後に一つ付け加えましょう。 一つでは足りないという場合でも、たくさん言うのはやめておきましょう。
最初に直してほしい点を言うと、保護者はそれが一番印象に残って、あとから褒めても効果は薄くなります。
逆に、全て褒められると、心配になる保護者もいます。たくさん褒めると、「先生、本当に心配なことはないんですか?」と聞かれることもあります。保護者は自分の子のダメなところを知っています。保護者ですからね。
確かに学校生活では、本当に立派で褒めるしかないという子もたまにいますよね。そういう場合、「本当に何事も問題なく生活できているのですが、優秀なだけに壁にぶつかった時が心配だと感じることはあります。」と答えたことがあります。
保護者が話したい場合は、聞き役になる


おしゃべりな保護者の聞き役になるという意味ではありません。おしゃべりな保護者であれば、適度な会話のキャッチボールができるので、こちらも伝えたいことを話せばよいです。
どういうことかというと、保護者が何か相談事をもってきた場合のことです。友達関係のこと、家庭環境のことなど、深刻な悩みを相談されることがあります。保護者は、「もうすぐ懇談があるから、そこで先生に相談しよう」と思って、しばらく我慢していることがあります。悩みが深くなっていることがあるので、保護者が話し始めたら、しっかりと聞いてあげてください。事前に準備したことは伝えられないかもしれません。しかし、保護者にとっては悩みを解決することが第一ですから、しっかりと聞いてあげることが大切です。



最初から深刻な顔をしていたり、手にメモを持っていたりした場合、何か伝えたいことがあると思ってください。
苦情は真摯な態度で聞く
苦情と言ってもいろいろあります。担任に対する苦情もあれば、他の職員や学校に対してかもしれません。感情的に言う人もいれば、ちょっと伝えたいというスタンスの人もいます。
どういった形であれ、苦情や要望については真摯な態度で聞きましょう。保護者に言いたいだけ言わせてください。大抵の保護者は一方的にしゃべると、「ちょっと言いすぎたかな…」と思い、こちらの話を聞く態度をもつようになります。(もちろん、まったく気にしない人もいますが)
保護者がまだ言い足りないのに、こちらが話そうとするとヒートアップする可能性があるので、注意が必要です。
教職員の悪口は言わない


教職員の悪口は絶対に言わないようにしましょう。保護者から、「〇〇先生の授業がわかりにくいです。」と職場の同僚のことを言われても、「そうですね。子どもたちも〇〇先生の授業がわかりにくいと言っているんですよ。」なんて答えてはいけません。
職場の仲間の悪口を言うことは、学校全体の信頼を下げることにつながります。決して悪口を肯定せず、上手に聞き流してください。ただ聞いてほしいだけという場合がほとんどです。
返答が難しいことは、即答を避ける
これは、若手の先生にぜひ気を付けてほしいことです。
時々、即答に困るような質問を受けることがあります。「安全のためにスマホを持たせたい」「学習発表会当日にどうしても急用で見に行けないので、総練習を見に行かせてほしい」など、自分の判断で答えてよいのかどうか迷う場合があります。
このような判断に迷う質問があった時、自分の判断で即答してはいけません。また、「いいんじゃないですかね」というような曖昧な返答も保護者を困らせます。



適当に答えてしまうと、「あの時、先生が言っていたことと違う!」と苦情を言われることにつながります。
そういう時は、「即答できないので、相談して後日連絡します」と答えましょう。
その場で答えられないからといって、保護者の信頼がなくなることはありません。むしろ、きちんと確認してくれる先生なんだと思ってもらえます。ただし、できるだけ早く返答しましょう。早ければその日のうちに、無理なら次の日には連絡をしましょう。
次の順番の人を待たせないように、時間を守る


若い先生の中には、保護者との話が切れずに、どんどん時間が延長してしまう場合があります。
時間が延長すれば、そのあとの保護者は待たされることになります。延長が続くと、あとの方の人は20分、30分と待たされることになります。
時間の都合をつけて学校に来てもらうのですから、できるだけ時間通りに進むようにしましょう。
長引きそうな場合は、「後の人の予定が入っていますので、もしお時間が必要でしたら後日また懇談を行いませんか。」と言えば、わかってもらえると思います。深刻な話の場合でも、正直に後の予定が入っていることを伝えましょう。
大切な話だからしっかり時間をとって聞きたいので、後日ゆっくり話をしたいと申し出れば、誠意は伝わるはずです。
どうしても話が長くなることがわかっている場合、最初からその日の最後に予定を組んでおくか、次の人との間をたくさん空けておきましょう。



話が長くなる保護者については、前担任などから情報を得ておきましょう。
まとめ
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
教員時代の経験をもとにまとめさせていただきました。職場の先輩や管理職などからも、いろいろと保護者との懇談で大切なことは教えていただけると思います。
保護者との懇談は、本当に大切だと思います。子どもたちを伸ばすための意見交換だけでなく、保護者からの信頼を得られる場にもなるからです。
ぜひ、懇談を上手に進めて、保護者や地域から信頼され、必要とされる教師になってください。
私の経験が少しでもお役に立てたら幸いです。